Blog
女医ヨガインストラクターSEIKOのヨガブログ :養うアーサナ☆
毎週土曜日13時から コミュニティークラスでトリートメントヨガを担当している
女医 兼 ヨガインストラクターのSEIKOです!
今日は、養うアーサナ☆について医師目線からお伝えします。
私個人の印象になりますが、ヨーガの教えの中には魅力的なフレーズが多くあると感じます。
例えばポーズをとっている時には、
自分の限界をリスペクトする、無理をしない、苦しくなったらいつでもポーズを離れていい、ジャッジせずにただ気付くなど、今の状態に寄り添ってくれるような表現があり安心したり心地よく感じます。
そこには受容があり、今の自分への愛が感じられたり、優しい気持ちになるのです。

今日は私の好きな言葉の一つ、“養うアーサナ“についてお伝えしたいと思います。
実は、アーサナ(ポーズ)は用途によって3つに分類されます。
- 1つ目はリラックスのアーサナです。(仰向けでとるシャバーサナ、うつ伏せでとるマカラーサナがあります。)
- 2つ目は瞑想のアーサナです。(蓮華座や達人座等、座る姿勢のことです。長く安定して座ることができるよう接地面積が広くなりますが、柔軟性や十分な関節の可動域を必要とするため、関節を痛めることがないように無理をしないことがとても大切です。)
そして
- 3つ目が養うアーサナです。(つまり、ポーズの大半がこれに当てはまります。)
養うアーサナ、
ヨーガの講義で初めてこの表現に触れた時、私が感じたことは、
アーサナってするものじゃないんだ、養うって表現が興味深い、というものでした。
今では、アーサナにはこの表現がとてもしっくりくると感じます。というのは、アーサナは進化していく、と認識しているからです。
例えば、体幹の強さや筋力、柔軟性等が必要で、初心者にとって簡単に最終形をとれないポーズがあります。
先日の特別クラスで練習したシルシャーサナ(いわゆるヘッドスタンド)もそうですし、
他の逆転のポーズ、ハーラーサナ(鋤のポーズ)等。
柔軟性が高かったり、手足が長かったり、ヒョイっとすぐ出来る方もいるでしょう。しかしそういう方ばかりではなく、個人差があるため最終形は当然ひとりひとり違ってきます。そして、ヨーガの練習では、自分の最終形を目指します。

例えば私の例ですが、ハーラーサナ(鋤のポーズ)を長期間をかけて練習しています。
一年位は準備のポーズを繰り返す練習を続けて、腹筋を養っていました。
因みに初めの半年位は、自分には出来ないポーズだと思っていて他人事のように何となく練習していましたが、後半はポジティブな気持ちで丁寧に練習を続けるようになりました。(態度が成長したとも言えます。)そのため、ある日突然ヒョイッとお腹の力でお尻が持ち上がり、身体の成長を実感した時はとても驚き、遅れてやって来たギフトに何とも言えない嬉しさを感じたものです。そんな経験から、私にとってハーラーサナは大切なポーズとなっています。

最終形が取れるようになってからも、練習の中でポーズは成長していきます。インドの先生から学んだことを意識してポーズを深めたり、その後ポーズをさらに洗練させることが出来ると知り、磨いていく練習を重ねたり。
そして、人に伝えるための練習へと続いている今の私も、もちろん道の途中です。
インドのベテランの先生でも、ただ道の少し先に立っているだけで私たちと変わらない、と仰います。
練習の内容には段階があります。ただポーズをとれているという状態から、より繊細にリラックスしてポーズを取る、さらにその状態で長くポーズに留まる等、練習は徐々に進化していきます。
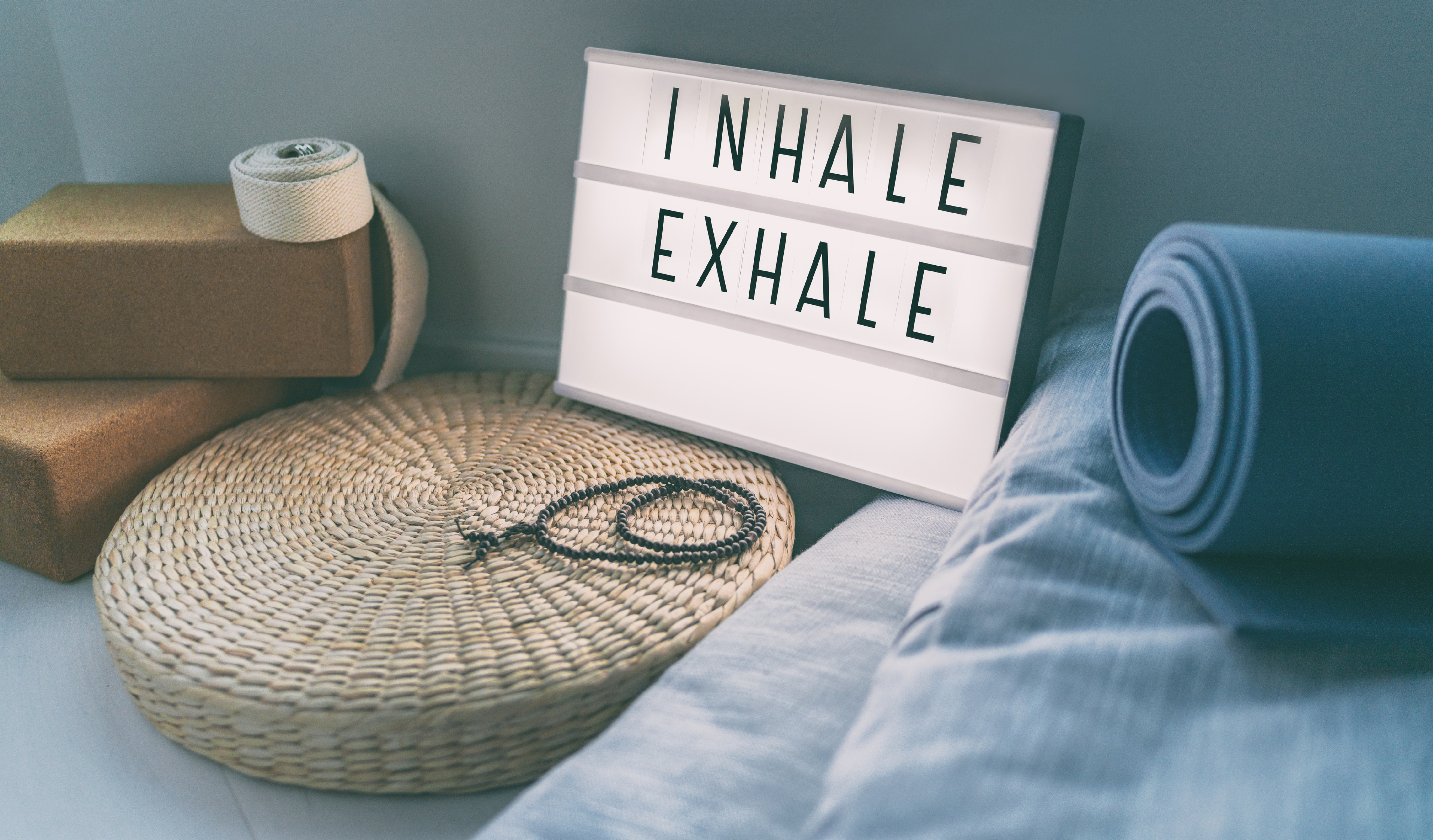
今どの段階にいるとしても、丁寧に練習を積み上げていくことは必ず何らかの結果をもたらします。柔軟性が養われたり筋力が鍛えられたり、あるいは自信だったり、心の安定や前向きな態度が得られたり。
身体と共に態度や心も養われていく感覚。実際にアーサナを継続して練習する経験を通して、これは自分を育てていく練習をしているのだな、となんとなく実感するようになりました。
もしかしたら、練習している時に自分は何かのポーズができないと思ったり、焦る気持ちがあったり、悲しかったり、あるいはポジティブな気持ちになりにくいこともあるかもしれません。
そんな時に思い出していただきたい言葉がこれです。
アーサナはするものではなく、養うもの。☆
アーサナは進化していくものです。練習を継続すること、それは私たちに確実に身体の状態、そして態度を含めた精神性にも成長の機会を与えてくれます。そのために大事なことは、心も身体も無理をしないこと。そして感情に影響を受けすぎずに、淡々と続けることのようです。
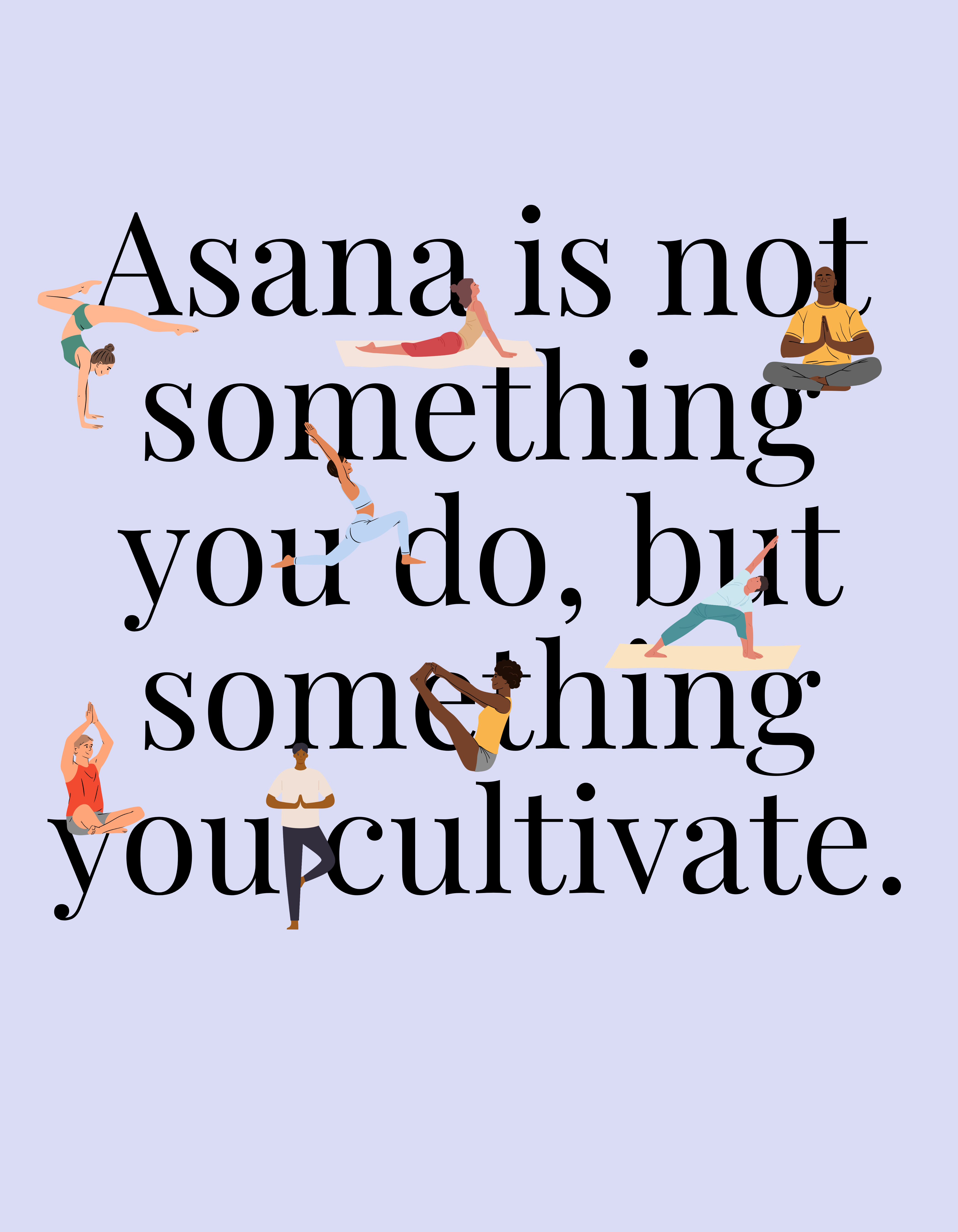
(ひと言MEMO☆ )急いで無理をしてしまうと、怪我をするリスクが上がります。大人の怪我は治りにくく、日常生活の質の低下に直結します。まずは少ないキープ時間で何度も繰り返す練習を行っていくことが身体の柔軟性や可動域を広げるのを助けてくれます。
あの時、『出来るようになりますよ』と先生に言われても、実感できなかった私ですが
今では、『出来るようになりますよ』と伝えていきたいです。(人間て変わりますね。)
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
トリートメントヨガにてお待ちしています。
SEIKO

